真田信幸の妻といえば小松姫(お稲)が有名ですよね。
NHK大河ドラマ「真田丸」では開始時点(天正10年・1582年)ですでに「こう」という名前の奥さんがいます。
小松姫が嫁いで来るのは第一次上田合戦(天正13年・1585年)のあと。
諸説ありますが、真田と徳川が和睦した天正17年(1589年)ごろといわれています。
ということは、小松姫の前に奥さんがいたのです。
じゃあ、小松姫が来たあとはどうなってしまうのでしょうか。
信幸の妻は複数いる
戦国時代の大名には正室と側室がいることはご存知ですよね。
大名でなくても、ある程度大きな武家なら正室と側室がいることは珍しくありません。
真田信幸は真田家嫡男です。
武家の例にもれず、正室と側室がいるのです。
信幸の妻として有名なのは小松姫です。
他に清音院、右京の局がいます。
小野お通という親しい女性もいました。
「真田丸」で「こう」となっている女性は、
歴史上は「清音院」と呼ばれる人です。
清音院
こうは小松姫以前からいた妻です。
生前の名前は分かっていません。
いつ生まれて、いつ死んだかも詳しいことは分かっていません。
資料が残ってないんですね。
戒名から 清音院 といわれます。
他の作品では真田殿(さなだどの)と書かれていることもあります。
「こう」というのはドラマの中での名前です。
このブログでも「こう」と書くことにいたします。
こうの父親は真田信綱。
真田昌幸のお兄さんです。
信綱は祖父・真田幸綱(幸隆)のあと真田家を継いでました。
でも、長篠の戦いで討死しました。
母は於北殿。
北信濃中野を本拠地にする、高梨政頼の娘とも妹ともいわれます。
実は、高橋内記(きりのお父さん)は於北殿の弟。
於北殿が真田信綱に嫁いだときに同行して真田家の家臣になったといわれます。
こうにとって高橋内記は叔父。こう と きり は従姉妹になるんですね。
ドラマでは全然かかわってきませんね。
今後もとくにかかわることはなさそうですが・・・
清音院と信幸が結婚したわけ
真田家を継いでいた父の信綱は長篠の合戦で討死しました。
後継者のいなくなった真田家を継ぐため、武藤家に養子に出ていた信綱の弟・昌幸が真田家を継ぐことになりました。
昌幸については 真田昌幸、武田家滅亡までの歩み を参考にしてください。
残された こうは昌幸の息子と結婚することになりました。
真田の名を継いだとはいっても昌幸は嫡流ではありません。
本家の娘と自分の長男(信幸)を婚姻関係を結ばせることで真田昌幸は真田家本流としての正当性を強化したんですね。
それが信幸とこうが結婚することになった大きな理由といわれます。
いとこ同士の結婚ですが、当時はめずらしくありませんでした。身内とはいえ政略結婚みたいなものです。
しかも当時の信幸は9歳か10歳。
こうの年齢はわかりません。
家を残すためとはいえ、幼くして相手を決められてしまうとは。武家とはたいへんです。
清音院は側室だった?
一説には病弱だったために小松姫が来る以前に亡くなったともいわれます。
ドラマでも病弱に描かれてます。いつ亡くなってもおかしくない雰囲気ですね。
でも、
通説では小松姫が来た後は側室になった、とされてます。
清音院が亡くなったのは元和5年(1619年)という説もあります。
ということは小松姫が来た後も生きていたことになります。
正室は一人でなければいけないというのは江戸時代に入ってからです。
側室は正室より下の身分の人。家来みたいなものです。正室が亡くなったからといって側室が昇格することはありません。その場合は継室を迎えます。
戦国時代までは正室が二人いてはいけないと決まっていたわけではないですね。もちろん、普通は正室は一人です。新しい正室を迎えるときはそれまでの正室を側室にするのではなく、離縁した例もあります(黒田長政とか)。
ドラマでも家康が「離縁させればいい」と言ってますが。
歴史上は離縁してません。
でも、正室が側室になることが絶対にないとはいえません。政治的な理由で家柄の高い娘を正室にしないといけないとき、実家の身分の低いほうが側室あつかいになることはあります。
でも真田本家の娘を離縁することはできませんよね。古くから真田家に使えている家臣は反発します。
極端な例では豊臣秀吉の正室は北政所(おね)ですが、当時の記録では淀君(茶々)や松の丸殿(竜子)も正室扱いになっています。
戦国時代の武家の妻に対して正室、側室と言っているのは江戸時代から後の人が勝手に決めてることがあるんですね。
小松姫は徳川重臣・本多忠勝の娘、しかも家康の養女です。側室にするわけにはいきません。そんなことをしたら徳川と真田との関係が悪くなってしまいます。
(あとで昌幸、信繁は徳川と敵対しますが・・・)
というわけで、清音院(こう)も小松姫も
当時の感覚としてはどちらも妻です。
小松姫が嫁いできた直後に書かれたと思われる資料では清音院のことを「御新造様」と書いています。御新造様とは家臣が本妻を呼ぶときの尊称です。将軍家であれば「御台所」と呼んでいたのと同じ感覚です。
ということは、少なくとも小松姫が来てもしばらくは本妻と認められていたということです。
ただし「御新造様不愉快」という書かれ方をしているので、清音院にとっても信幸と小松姫の縁談はこころよく思ってなかったのかもしれません。少なくとも最初はショックを受けたでしょう。
でも、親のいない清音院と実家が徳川重臣の小松姫では影響力がまったく違います。事実上は小松姫が正室として仕切っていた可能性はあります。
江戸時代になると正室は小松姫というのが、世間的には広まったと思われます。
真田家存続のためには、表向きだけでもそうしておかないとまずいのです。
ちなみに、もうひとつの真田ドラマ・真田太平記では清音院は最初からいないことになってます。信幸は小松姫一筋。という描かれ方をしています。
なんとも薄幸な人なのです。
天正17年(1589年)、豊臣秀吉は全国の大名に京に妻子を住まわせるように命令します。つまり人質です。
このときは小松姫はまだ嫁いでなかった可能性があるので、清音院が京に行ったのかもしれません。昌幸の正室、つまり信幸の母・山手殿(薫)も京に行くことになります。
その後、文禄4年(1595年)長男・信吉が生まれます。子供が生まれたということは小松姫が来たあとも信幸と清音院の仲は悪くなかったということでしょう。
慶長4年(1599年)、信幸は大坂に人質になっていた妻子を「女中改め」と称して引き上げてしまいました。ようするに、家庭の事情で大坂から妻子を出してしまったのです。当時徳川家康が勝手に妻子を引き上げていることは石田三成も問題にしていました。その中に信幸の妻子もいたのかもしれません。つまり石田三成が挙兵する前から、信幸は徳川家康に味方するつもるだったといえるかもしれません。
関ヶ原以降
関ヶ原の合戦では信幸が味方した徳川家康が勝ちました。信幸は真田家の当主、そして上田藩9万石の大名となりました。
このときには嫡男信吉と共に信幸の居城である沼田城に戻っていたと思われます。
江戸時代になると徳川に忠誠を誓う大名は妻子を江戸に住まわせるようになります。家康の時代はまだ強制ではありませんでした。
でも忠誠心を示したい大名家はこぞって江戸にすまわせました。
生き残ったとはいえ、真田家は昌幸時代には徳川と対立していました。
真田家としては徳川に忠誠を示す必要があります。
江戸に妻子を住まわせることになりました。
予想ですが、清音院が沼田で暮らして小松姫が江戸で暮らしたのではないでしょうか。
徳川家とのつながりがある小松姫が江戸でいたほうが都合が良かったはずです。徳川に対しては小松姫が正室というということをアピールしなければ立場が危なくなります。
清音院は真田家嫡流の家柄。
古くからの真田家臣にとっては心のよりどころとなったかもしれません。
(ドラマではそんな描かれ方はされてませんが)
系図から名前が消えた
江戸時代になって、幕府は各藩に大名家の系図を提出させました。
そのとき、清音院は「家のもの」と書かれてました。
「身分の低い人」という意味があります。
ただし、これは幕府に提出する書類です。
大名家は徳川家にかなり気を使ってます。
真田家は小松姫を立てないといけません。
清音院が正室の立場にいるとまずいことになります。
身分の身分の低い人とあえて書いたのは、
あくまでも表向きのことだと思ったほうがいいかもしれません。
清音院のしたことが小松姫の手柄に?
昌幸・信幸は関ヶ原の合戦あと九度山に流刑になりました。
真田家からはお金や物が仕送りされました。
信幸や小松姫が送ったといわれています。
でも、清音院だった可能性もあります。
歴史の資料では「信之の妻が送った」という書かれかたをしています。
小松姫かこうなのかどっちが送ったのか分からないんです。
現代人は信之の妻=小松姫と思ってるから、小松姫が送ったことになってるんですね。
一方は本国。一方は徳川の人質として暮らしたのではないでしょうか。
それぞれの場所で真田家を支える妻としての役目をはたしていたのかもしれません。
清音院は、元和5年(1619年)、亡くなったといいます。
大河ドラマ「真田丸」では。
稲(小松姫)が嫁いでくると、離縁されてしまいます。
それなのに侍女として残るという、現実にはありえない展開。
でも、こうの活躍はここからなのです。
稲にとっても信幸にとっても重要な存在になりそうな予感です。
関連記事
清音院の夫
清音院の息子
清音院の親
同じ夫を持つ女性
清音院の叔父(母の弟)

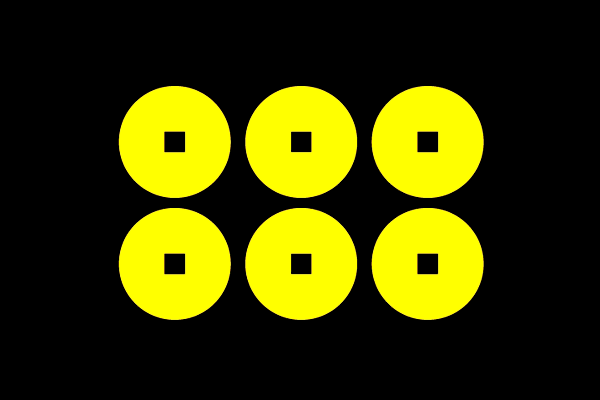
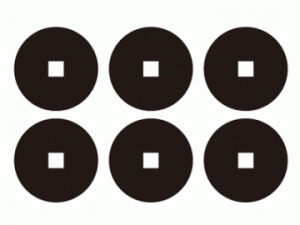
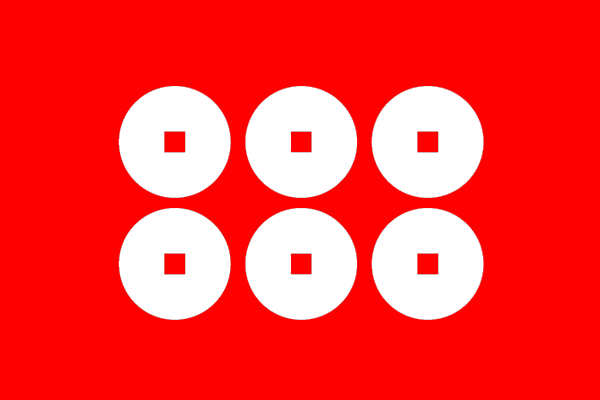
コメント
文也様。こんばんは。こう、真田丸でなかなかのキャラですよね!信綱と於北の子だから、信之も信繁も松、きりは従兄弟なんですよね。放送ではエピソードが無いので分かりにくいですが歴とした真田家の血を引き、病弱ながらも信之を支えようとする姿が印象的です。
コウイチ様。こんにちは。こうは重要な血筋のはずなのにコメディ調のキャラなのが気になりましたが、家が第一と考える様子は戦国の女性らしさを感じます。病弱なので小松姫が来るまでに死ぬんじゃないかと心配してました。でもこの様子だとずっと生きていそうですね。
信之が93歳の長寿だったことは成り行きでは達成不可能な大偉業でした。
ピカソも同じくらいの長寿でした。彼はキャンバスの中で女性を犯していた。
ピカソの方が隠すことは下手だけど人間臭くって面白い。
信之に対するコメントが余りにも優等生回答が多くてがっかりです。そんな
理由で長生きなんかできない。隠された明確な目標が存在し、それを知りたい。
picaso9672さんこんにちは。なかなか面白い記事を書くのは難しいですね。もっと人間味あふれる文章を書けるようになりたいです。
はじめまして。当方、清音院殿の研究をしている者です。ひと通り読ませていただきました。
少しだけ修正をお願いしてもよろしいでしょうか?
高梨内記と於北(高梨家)は無関係の可能性が高いです。
高梨家系図にも、内記は書かれていません。よって、清音院殿とも血縁関係にはなかったと思われます。
あと、「御新造様」についてですが、これは小松殿のことです。どの資料をお読みになったかがわかりませんので、こちらの資料で申し上げますが、「御新造様」が出てくるのは、確か小松殿が入輿する際に「御新造様御不快」というところからだと思います。この「御新造様」は小松殿ことで、「御不快」とは「病気」の意味です。よって、「小松殿が病気になったので、輿入れをする日を延期した」、という内容のものになります。
また、小松殿が江戸へ人質として出府したのは、少なくとも慶長十一年以降です(本多忠勝書状中に「沼田にいる娘にもよろしく伝えて欲しい」という一文がある為)。もっと言えば、関ヶ原以降、江戸へは山之手殿が人質として出府していますので、山之手殿が亡くなった後、慶長十七年以降ではないかというのが、現在有力な説です。清音院殿がどこにいたかはわかりませんが、可能性として江戸が考えられます(江戸から信之家臣に宛てた、「久」とういう女性の書状が清音院殿ではないかと言われています)。
長々と書いてしまい、すみませんでした。
ちかこ様こんにちは。高梨内記と於北については様々な説があるようですね。内記自身謎の多い人物なのではっきりしたことは言えないのかもしれませんね。御新造様が小松姫の可能性については、おっしゃるとおりかもしれません。小松姫が人質になった年についての考察は興味深いです。詳しい情報ありがとうございます。