 1 古代
1 古代反正天皇 兄のため、謀反を起こした兄弟を暗殺して次の天皇に
反正天皇は第18代の天皇。 5世紀に存在した大和の大王です。 古代中国の歴史書「宋書」「梁書」にある倭の五王の「珍(彌)」にあたる人物ではないかともいわれています。 反正天皇とはどんな人だったのでしょうか。 反正天皇という諡号は奈良時代に付...
 1 古代
1 古代 1 古代
1 古代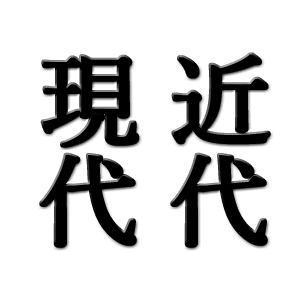 7 近現代
7 近現代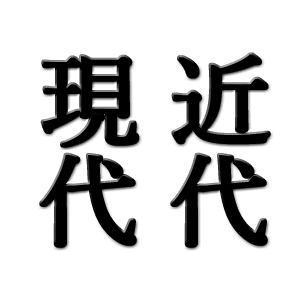 7 近現代
7 近現代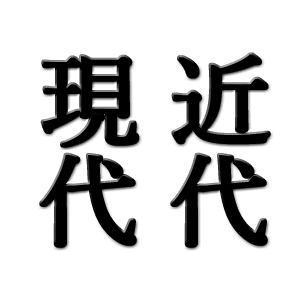 7 近現代
7 近現代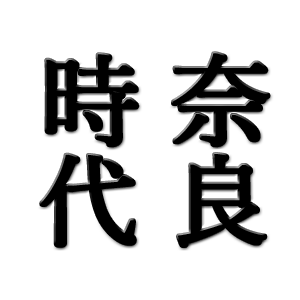 2 飛鳥時代
2 飛鳥時代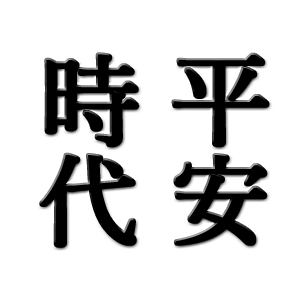 4 平安時代
4 平安時代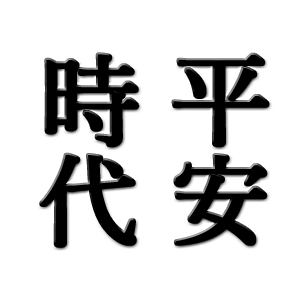 4 平安時代
4 平安時代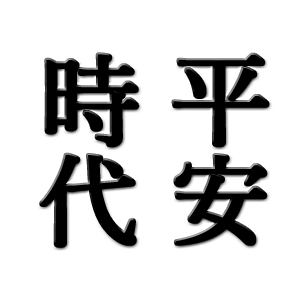 4 平安時代
4 平安時代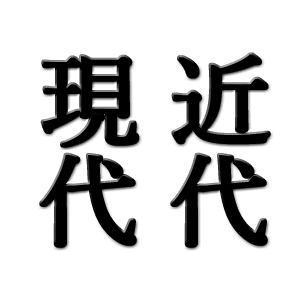 7 近現代
7 近現代 イベント
イベント 史跡名勝
史跡名勝 史跡名勝
史跡名勝 6. 江戸時代
6. 江戸時代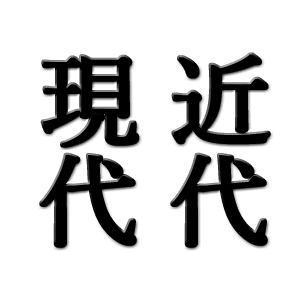 7 近現代
7 近現代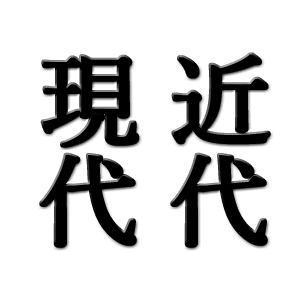 7 近現代
7 近現代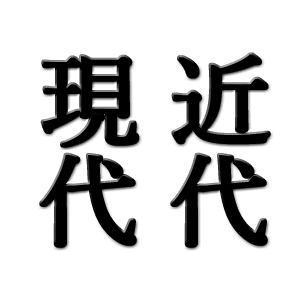 7 近現代
7 近現代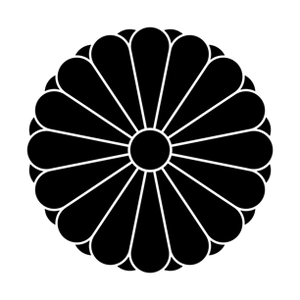 6. 江戸時代
6. 江戸時代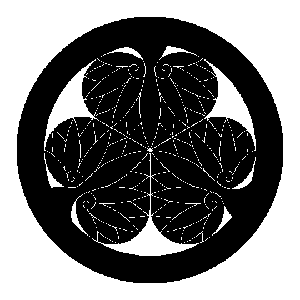 6. 江戸時代
6. 江戸時代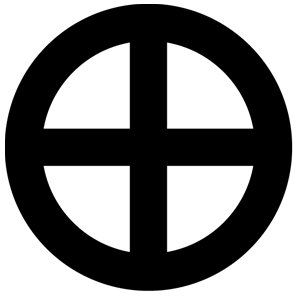 6. 江戸時代
6. 江戸時代